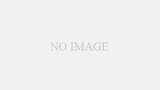宅建業法になじみのない人からすると、「不動産屋」=「宅建業者」のようなイメージがあります。しかし両者は全くの別物です。
自分の建物を貸す業務は「宅建業」ではない
私のように不動産を購入して人に貸している不動産大家は、宅建業者ではありません。あえて表現するなら「不動産賃貸業者」とでも言いましょうか。
「不動産をやっているんなら、宅建持ってるんでしょ?」
と質問されることもありますが、私は(まだ)宅建を持っていません。これから取りたいとは考えていますが。宅建を持っていなくても、家を人に貸すことは問題ありません。特に違法行為をしているわけではないので悪しからず。
家を建てる業務も「宅建業」ではない
ゼネコンや工務店など、住宅をつくる業者さんも宅建業者ではありません。建設業者です。家を建てるにあたって、宅建は必要ありません。
サブリースも「宅建業」ではない
「一括借り上げ」などのサブリースを行っているサブリース業者も宅建業者ではありません。借主兼貸主になります。
「宅建業」とは?
宅建業法では、以下の3つの業務が「宅建業」として定義されています。
- 自分の宅地・建物の売買(交換)を業として行う:当事者
- 他人の宅地・建物の売買(交換)・賃借の代理を業として行う:代理
- 他人の宅地・建物の売買(交換)・賃借の媒介を業として行う:媒介
所有している家を直接販売するには、宅建が必要になります。建売住宅などを売っている分譲業者が上記の1.に当てはまります。「分譲」という行為は、宅建業法では「当事者」と呼ばれます。
売主と買主を仲介するにも宅建が必要です。通常の不動産売買が「不動産屋」さんを通して行われるのはこのためです。この「仲介」という行為は、宅建業法では「媒介」と呼ばれます。
新築マンションの分譲の際、売主だけでは販売が追いつきません。「販売代理業者」に販売の代理を依頼することがあります。この販売代理行為は「代理」と呼ばれます。
「一括して売却」なら宅建は不要
所有している土地を売却する場合、一括して売却するのであれば宅建は不要です。しかし、その土地を分割して複数の買主に「分譲」する場合には、宅建が必要になってきます。
「転売業」には宅建が必要
前述の「宅建業とは?」の部分で、「業として行う」という言葉がありました。
次の二つの要件を満たす場合は「業」と呼ばれます。
- 不特定多数を相手に取引をする
- 反復継続して取引を行う
「中古住宅を仕入れて売る」といういわゆる「転売業」の場合は、宅建「業」の当事者と判断される可能性があります。
賃借に関しては当事者には当てはまらないため、反復継続しても宅建業者にはなりません。
宅建が不要なケース
宅建を持っていなくても宅建業を行うことが許可されている法人もあります。
- 国
- 地方公共団体
- 都市再生機構
- 地方住宅供給公社
- 信託銀行
- 信託会社
などです。
ただし、信託銀行と信託会社に関しては、宅建業法の規定は適用されますし、国土交通大臣への届け出も必要です。
まとめ:大家さんに宅建は不要だが、持っておいて損はない
宅建がないと不動産投資ができないわけではありませんが、持っておいて損はありません。仕事の幅が拡がりますし、「不動産屋」さんと対等な知識を持って渡り合うこともできるようになります。試験本番は10月16日とずいぶん先ですが、徐々に学習を進めていきたいと思います。
以下の書籍を参考にしました。
![合格しようぜ! 宅建士 2016 音声付きテキスト&問題集 上巻[宅建業法・法令上の制限] 合格しようぜ! 宅建士 2016 音声付きテキスト&問題集 上巻[宅建業法・法令上の制限]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61AxN7ZlueL._SL160_.jpg)
合格しようぜ! 宅建士 2016 音声付きテキスト&問題集 上巻[宅建業法・法令上の制限]
- 作者:宅建ダイナマイト合格スクール 大澤 茂雄
- 出版社:インプレス
- 発売日: 2015-12-17